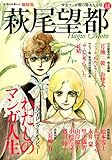読んだ本とか、漫画とか、映画とか、色々

編集長の仕事にも恋愛にも行き詰った梨央、30歳。ある日、酔った勢いで建設現場の足場に登り、降りられなくなったところをトビ職の徹男に助けられる。徹男に一目ぼれした梨央は、勢いで工務店に飛び込み就職。だがそこは、亭主に逃げられやむなく社長になった郷子がキレる寸前で大混乱中だった。女ふたりの行く末はいかに!?(裏表紙より)
面白かった! 30歳女性と、ずっと専業主婦だったのに工務店の社長をやることになった女性が、それぞれ仕事に向けて何かを見いだしていく話。
文章が小気味よくて好き! 梨央は途中くらいまで恋愛脳なのかなと心配になったけれど、段々と仕事にやりがいを感じていくところはかっこいい。すごくきらきらしてる。
お話もあんまり恋愛しているわけじゃなくて、とことん自分磨きというか、自分がどれだけできるのかを探していくものだったので、そういう自立心の強いところがある女性陣は本当にいい。仕事をすることに付随する人間関係の摩擦や仕事のやりくり、悩みなんかも、彼女たちなりに付き合っていくところとか、爽快! というわけではないのに、しみじみ、いい話だな! と思う。一言で言い表すなら楽しかった、かな。
オススメされた本でした。ありがとうございました!
PR

浩志は、父親の再婚をきっかけに家を出た。
壁に囲まれた路地を入り、「緑の扉」を開いた浩志を迎えたのは、高校生の一人暮らしには充分な広さの部屋と、不可解な出来事。無言電話、奇妙な落書き、謎の手紙etc.
そして、「出ていったほうがいいよ」と呟く和泉少年の言葉が意味するものは……。
嫌がらせ? それとも、死への誘い!?
——怖い——。しかし浩志の家は、もはやここ(・・)しかない! 息をもつかせぬ本格ホラー。(カバー折り返しより)
昔『過ぎる十七の春』を読んだときにぞぞっとしたのですが、今回もひいっとなりつつも、その怖さが面白かったです。「絶対に許さないよ」は怖い。
少年の罪、異界との境界にある家。悪意なのか、怪奇なのか。救われるものもありながら、決して動かせない異界がある。日常の中に入り込んだ恐怖をきっちりと描くとこんなお話になるのかと、面白かった。

コンビニ強盗に失敗し逃走していた伊藤は、気付くと見知らぬ島にいた。江戸以来外界から遮断されている“荻島”には、妙な人間ばかりが住んでいた。嘘しか言わない画家、「島の法律として」殺人を許された男、人語を操り「未来が見える」カカシ。次の日カカシが殺される。無残にもバラバラにされ、頭を持ち去られて。未来を見通せるはずのカカシは、なぜ自分の死を阻止出来なかったのか?(裏表紙より)
デビュー作だったのか! はー面白かったー。一人称で進むお話なので淡白で薄い主人公なのだけれど、周りが濃い。手に汗握る面白さというよりも、淡々とした世界とシュールな設定の中のものが、どう結びついていくのかが面白い話だった!
閉ざされた島での奇妙な日々。そこに外の世界からもたらすものは何なのか、というのを、カカシ殺人事件から始まった謎の裏でずっと問われ続けてくるのだけれど、この、最後の! ずっと「島に欠けているもの」が何なのかというものが分かったとき、思わずぶわっとこみ上げてしまった。
好きな小説だった!

絶望的な恋をしているのかもしれない。私がやっていること、全部、無駄な足掻きなのかもしれない。——それでも私は、あなたが欲しい。
美大生の春川は、気鋭のアーティスト・布施正道を追って、寂れた海辺の町を訪れた。しかし、そこにいたのは同じ美大に通う“噂の”由良だった。彼もまた布施正道に会いに来たというが…。
『プシュケの涙』に続く、不器用な人たちの不恰好な恋の物語。(裏表紙より)
何シリーズと呼ぶべきか分からなかったので調べてみたら、由良三部作というんですね。その二巻目です。
美術系アーティスト・布施正道を追ってきた春川が由良に出会い……という、やっぱり由良が語り手振り回すのかという話なのですけれども、それがやっぱり心地いいというか、お約束で楽しいです。
語られる内容は少しシリアスでえぐいところもあるけれど、この、ひたひたと陰が感じられるのがこの一連のシリーズが好きなところかなと思います。
二編目のグラビアアイドル・Aの話は、好きだなー。女の子の本音好きだなー(笑)という、刺々しく生々しく生意気でありつつかわいらしい、歪んだ女の子の視点から語られる話で、こういうしたたかなのがいいのよ! と思いました。
女の子ってーのはゴボゴボと血を流しながらニッコリ笑って仕事するのだ。
狙ってるよね。狙ってるよこの一文!
オススメされた本でした。ありがとうございました!

(助けて。助けて、颯音——!)
遠雷の咆哮を響かせ、牙を剥いた獣が鳴に襲いかかる。鳴の意識は、闇へと落ちていく。
——二人でともに生きる
颯音と交わした約束を何度も繰り返しながら。
激しく地が震えた。
春惜月の出来事から一月。城下町で「狐」の情報を集める鳴と颯音。しかし、青津野の巧妙な罠により鳴は敵の手に落ちてしまう。鳴を救い出すため、そして自らの過去に決着をつけるため、颯音は青津野に反旗を翻した領民らと共に町へ突入する。そして、遂に宿敵・青津野刑部がその本性を現す——!
大いなる戦の前触れに揺れる、時は五百年の昔。異能の力故に“業多姫”と呼ばれ恐れられた少女と、心を持たない間者として育てられた少年。孤独な二つの魂が出会い、全ての運命は動き出した——。
第二回富士見ヤングミステリー大賞準入選作「業多姫」シリーズ、遂に完結! これは、戦乱の世を駆け抜けた、少年と少女の物語——。(カバー折り返しより)
業多姫シリーズ完結巻。ほぼ一年くらいかけて本編と外伝七冊を読んだ。長かった。
青津野との決着、颯音の過去、そしてすべての秘密が明かされる六乃帖。ページをめくるたびに謎は解けず深まるばかりで、鳴と颯音は離ればなれになってしまうし、本当にこれは完結するのだろうかと別の意味でもどきどきしました。
一年の長くも短い二人の旅路は、困難の方が多く、それでもささやかな幸せやお互いの結びつきを見いだしていく鳴と颯音が切なくも愛おしく、最後のページはとても幸せな気持ちで読みました。
ありがとうございました。

絵のヌードモデル、引きこもり新鋭画家、女装の麗人、ゴスロリ小学生、ネコの着ぐるみ、妄想癖の美女、不気味な双子の老人たち——〈鳥篭荘〉に棲みついたちょっとおかしな住人たちの、だいたいフツーでだいぶおかしな日常をつづる物語第4弾。——今回のお話は、着ぐるみパパがお見合い!? 山田家と加地家を巻きこんだちっちゃな事件簿(第1話)。浅井と由起の弟妹がやってきた。ところが浅井と由起が大喧嘩して……(第2話)。鳥篭荘随一の変人・へれんさんのフィアンセ登場。しかしへれんさんはフィアンセを拉致監禁!?(第3話)。浅井がキズナにモデルの解雇を通告、さらに鳥篭荘から住人立ち退きの噂が——など急展開の全5編を収録。(カバー折り返しより)
変人たちの暮らす鳥籠荘の物語第四巻。出てくる話やひとつひとつの設定や細かいところは悪趣味なのに、ちゃんと王道を押さえている感じがにくい! 好きだー!
画家とモデルの関係が、読んでいくうちに段々おいしくなってきた。メインストーリーが有生とキズナと由起の話で、この三人が、若く惑えるがゆえに愛おしくて。ちょっとした青春、だよなあ。二十歳くらいまでってそんなものだよなとか。にやにやしてしまう。
子どもの対象喪失―その悲しみの世界
1990年の本。
内的外的問わず、愛着や依存する対象を何らかの理由で失うことを「対象喪失」という。子ども大人問わず起こることで、人間が生きることにおいて、大小問わず必ず起こっていることである。
という愛着と依存対象の喪失について、事例を提示しつつ書いています。「対象喪失の心的世界」「対象喪失による病理現象」の二部構成です。中では、童謡や、児童文学などの文学作品の対象喪失について論じているところもあり、読み物として面白く、非常に興味深い分野だった。
1990年の本。
内的外的問わず、愛着や依存する対象を何らかの理由で失うことを「対象喪失」という。子ども大人問わず起こることで、人間が生きることにおいて、大小問わず必ず起こっていることである。
という愛着と依存対象の喪失について、事例を提示しつつ書いています。「対象喪失の心的世界」「対象喪失による病理現象」の二部構成です。中では、童謡や、児童文学などの文学作品の対象喪失について論じているところもあり、読み物として面白く、非常に興味深い分野だった。