読んだ本とか、漫画とか、映画とか、色々

時は中世。公国の若き領主、ジェイマス五世の老摂政が亡くなった。先見の明をそなえた摂政が国のために講じておいたとっておきの秘策、それは自身の飼い猫、ニフィだった! 賢い猫はやがて“摂政”として、重要文書承認時など敏腕ぶりを発揮。領主の恋に政治的陰謀が絡まりだすとき、隠れ摂政はどんな妙手を繰りだす? 猫を愛する現代SFの女王が贈る、猫ファンタジイの逸品。(裏表紙より)
なんとなく児童文学っぽい雰囲気のある話だなあと思いました。訳のせいでしょうか。会話の内容やテンポがなんとなくそう思わせたのかもしれない。
猫が活躍するという話ですが、視点はジェイマス公がメインで行くので、猫のニフィは裏方です。それでもところどころで現れて、あくまで猫らしい行動で人々の意表をつく解決策を提示してしまうのはすごく愛らしい! でもニフィも愛らしいですが、登場するエスファニア公国の人々も、理知的で機転が利いて、チャーミングな人たちばかりだと思う。
なんとなく、最後に亡くなった老摂政マンガンが笑っている気がしました。
ところでこの本、妙に紙が固くて捲りづらいです……。私のだけかな。
PR

冬の朝、陸橋から落ちてトーマは死んだ。同じ学校に通うユーリに遺書と考えられる手紙を残して。しかし時期外れの転校生エーリクが現れる。彼は死んだはずのトーマにそっくりだった。オスカーは、ユーリとエーリクの間に入り、変化を見守ることになるが。
萩尾望都『トーマの心臓』を核に、森博嗣の『トーマの心臓』に仕立てたという感じでした。『トーマの心臓』と銘打っていても、この作品の舞台は日本で、彼らはどうやら理系の大学生っぽい。名前は大体の人が渾名。双方がどのように関係しているのかと考えるのが面白い。
原作の知識がないと、ユーリとエーリクの関係性やユーリ自身の昇華は見られないのではないかな。原作では重要な役回りをしていたオスカーの目から見たユーリたちというのは、何故だかとても静かな、祈りのような、心や精神といったものに満ちている。そしてこの作品も、原作も、影響し合ってとても濃い深みを作っているように思います。

目覚めると名前すら思い出せず、今までの記憶を失くしていた少女に、端整な顔立ちの青年、秋里は「お前の名前は荘曄香。私の許婚だ」と告げる。
立派な邸での生活に違和感を覚える曄香だったが、優しく思いやりに溢れる秋里に次第に惹かれていく。
が、ある日、秋里の正式な許婚と名乗る琳国の公主、麗媛が邸にのりこんできた。
私は何者なの? 悩む曄香に隠された真実とは!?(裏表紙より)
花嫁じゃない! けど恋愛ものです。話は、本当に「はじめの地点」に戻る話でした。何にも解決してない気がするよ! ただすれ違いと甘やかしの話だけだった。記憶喪失と婚約者の公主というおいしい設定があるのに、一冊だけだったのは足りなかったような気がするもったいない!
でも終始漂う「私は誰なの?」という切なさとか、戸惑いが、なんだか切ない系スキーには肌に馴染みました。
時代背景がちょっと分かった。『蘭契の花嫁』の時代かー。この時代は閃国が二代目になって各国を併呑していたと。

海に嫁いだ乙女の伝説が生きる国・ガルトリア。開港祭の喧騒の中、天涯孤独の修道女ボニーは両親の仇である青年海賊ファド・ディアスと出会う。潔白を主張する彼の姿に、真実を求めるボニーはあえてファドに「さらわれる」ことを選択! 修道院へ連れ戻そうと迫る騎士団から逃れ、“危険すぎる”海賊船・マディラ号に乗り込むが……!? 恋を禁じられた修道女と、華麗で紳士な海の悪党——息もつかせぬときめきと冒険!
第12回えんため大賞《優秀賞》、ガールズノベルズ部門史上最高評価の快作が登場!!(裏表紙より)
修道女と海賊もの。爽やかで気持ちよかった! 生きること、運命、信じるものを、大切にしている人たちの話だったなあと思います。
最初は単純に甘いだけの冒険話なのかなあと思っていたんですが、事件があり、狂気がありでした。狂気には特にびっくりしました。でも最後に笑えるところになっていて面白かったです。名前も知らなかったくせに寸法のあったドレスはこわいな。レオノールが諦めてしまったところ、ちょっとすんなりで残念だったです。
ジジ専、渋専の私としてはバスカーがたまらんかったです。少女小説でおじいちゃんが出るとは!

生まれて初めての合コンで『新選組!』を語る、クリスマスイブに実家でイモの天ぷらを食す、非常にモテる男友だちの失恋話に相槌を打つ——思わず自分でツッコミを入れてしまう微妙さに懊悩しつつ、それでもなぜか追求してしまう残念な感じ。異様にキャラ立ちした家族や友人に囲まれ、若き作家は今日もいろいろ常軌を逸脱中。爆笑と共感がこみ上げる、大人気エッセイシリーズ!(裏表紙より)
クウガとオダギリと漫画とバクチク、がこの本の構成要素と言えるかと(それ以外もちゃんとあるけれど)笑った笑った。エッセイが読みたいなーと思うときは、大体この方の本を読みたくなるんだ。裏表紙の紹介の「キャラ立ちした家族や友人」というのが絶妙すぎて、これを書くために打ちながら噴いてしまった。
面白い日常もいいけれど、本の紹介が素敵で読みたくなる。

夢をかなえるために入学した高校で、希望に燃えていたみかげだが、気の合うともだちもみつからず浮かない日々。京都の高校に進んだ瞬と心を通わす手段は、メールでのやりとりだけ。人間関係も、恋愛も、うまくいかないもどかしい気持ちを携え、みかげは夏休みの間を京都で過ごすため旅だった——。
少女の成長と淡い恋の行方を瑞々しく描いた、ピュアな青春ストーリー!!〈解説・藤田香織〉(裏表紙より)
前作は家族ものでしたが、今作は少女たちと女性たちの物語の印象が強かったです。
主人公のみかげと、元クラスメートのエリサ。少女のような継母の洋子。京都のサワと涼。彼女たちの人生が、ゆるやかに絡み合いながら、サワ、涼、洋子が、みかげとエリサ二人の少女を大人へと導いていく、というお話であったように思います。
一人称で書かれているものの、作者の暖かなまなざしが感じられて、光丘さん自身が涼さんたちと一緒になってみかげたちを導いている気がするなあと思います。ふわふわと温かなお話でした。
そんな感じなので、恋の行方というほど瞬が関わってくるわけではなくて。それでも、心穏やかになれました。

中3のみかげは、亡くなったママのことを忘れられない。父親の再婚で兄妹になった同い年の瞬とはソリが合わない。でも、「ぶっきらぼうなやつ」としか思っていなかった瞬の存在が、だんだんと心の中で大きくなり始めて——。
少女の揺れ動く感情を縦糸に、じれったい「初恋」と家族の再生を横糸に織りなされた、純粋すぎるほどの青春模様。文庫書き下ろし。〈解説・小手鞠るい〉(裏表紙より)
思ったほど血のつながらない兄妹ものではなく、思った以上に家族の再生が描かれた話でした。
みかげの視点から語られる物語。みかげは、中学二年生にしてはちょっとだけ大人びていて、けれどママに執着する様は幼くて。その奇妙なギャップというのか、すんなりと納得して、周囲に対応したかと思えば、思いもがけないところで反発したりむっとしたり声を荒げたり。不思議な感じでした。
元々児童文学として書かれたものを下敷きにしているとあとがきにあったので、この純粋さはそうなのだろうなあと思いました。

新書を買うのは実は初めてである。森博嗣さんということが一番のネックで、小説を書くことについて書かれている本だったので、思わず衝動買い。……すっごく面白かった!
森さんが、すごく特異(?)な経歴と戦略で小説家になられた方なので、森さんの小説論がすごく興味深くて面白かった。小説を書くのに「小説を読むべきではない」というのもおおっと思ったけれど、出版業界、マーケティングについても述べられていて、やっぱりこの方すごい方なんだ! と思うことばかりでした。
出版業界って、実はすごく頭が固い業界なのですね。古来の日本人らしい、へんな暗黙の了解がまかりとおっているようだ……。不振の出版業界と、これからの作家と出版についても、すごく面白かった。
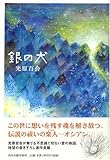
祓いの楽人(バルド)は天分の才。楽を奏でる者であっても「選ばれる」もの。世界の理を正す者。物言わぬ祓いの楽人オシアンと、彼と共に旅するブランは、この世に留められる、あるいは留まる頑な魂を解放し、理を正す者である。ケルト民話・伝説を下敷きにした異世界ファンタジー。
私が読んだのはハードカバー。文庫でも出ているようです。
とても綺麗なお話でした。一話完結、話の語り方は違えど、祓いの楽人オシアンと相棒ブランが、この世に留まった魂を解放する物語です。妖精、悪霊など、幻想の生き物たちがごくごく自然に人間に関わっている土地でのお話。ヨーロッパの妖精物語系でしょうか。
森の緑や湖の青なんかが活き活きと綺麗だなあと思いました。荒野の様子や、家々の様子なんかも、とても温かみのある、自然のままの世界で、こういう場所なら「万物の始まりは楽の音」と言われても全然不思議じゃない。
ハードカバーの、水彩の絵がとっても綺麗なのですよねー。気になってた本だったのですが、2009年冬号の活字倶楽部だったかで紹介されていたので、読んでみようと。とてもいいファンタジーでした! オシアンの謎も、ブランの物語も、まだ語られていないので、もし続きが出るなら読みたいです。

